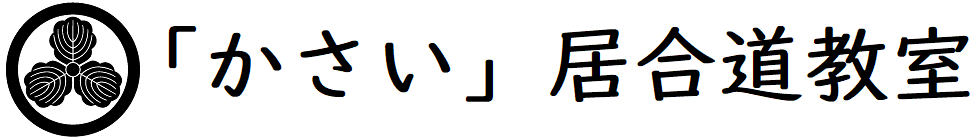居合道とは
居合道の歴史
居合(他に居合術、抜刀術、抜剣、抜合、坐合、居相、鞘の内、利方などと呼ばれることがある)とは、日本古来より伝承される日本刀を用 いた剣術のひとつです。
その起源は、戦国時代から江戸時代初期の頃に始まったとされています。
呼称の由来は、剣道のように刀を抜いて敵に相対してからの対敵動作「立合」に対して、居合は刀が鞘の中にある状態から坐って(あるいはその場に居て) 立合に至るまでの対敵動作であることから「居合」と言われています。
居合の特徴は、坐位または歩行中において、敵の不意の攻撃や組討の際に鞘の中から瞬間的に抜刀し、攻撃(斬る、突く)あるいは防御(受ける)から攻撃 へと移って敵を倒すところにあります。
こうした古武道である居合が、先人の研鑽(けんさん)や継承・発展の御尽力によって今日に至るまで連綿と伝わり、現在では武道として「居合道」と呼ば れています。
【武道と武士道】
実戦剣法に主眼が置かれた頃の居合は、武士個人の戦闘技術として 「武術」や「武芸」、「兵法」などと言われていました。
そしてこれらは、時代の移り変わりとともに「心の修養」としての要素が加わり、「武術」や「武芸」、「兵法」から「武道」へと変化を遂げました。
つまり、単に殺傷技術を身に付けるだけではなく、それを扱う人そのものの人間性の向上や精神の修養を含めて身に付けることを目的とし て「武道」へと変わった訳です。
さらに、この「武道」に必要な教養や道徳、倫理などが「武士道」となります。
当会の修得内容
当会では、「四神一刀流居合道」を修得しています。
これは荒木無人斎流居合道を基本として当会が考える四神(しじん)の思想を取り入れた新たな居合道(一刀兵法)として、命名したものです。
特徴は、単に「形」を覚えるのではなく、「剣理」を修得することにあります。
また当会における四神の思想とは、方位神(東:青龍、南:朱雀、西:白虎、北:玄武)を剣士の人生四季(春:青春、夏:朱夏、秋:白秋、冬:玄冬) と考え、「それぞれの方位(季節)の守護神に精進の誓いを立て、神の御加護を得る(宗教的意味ではなく、剣士として真剣に稽古に励み、成長と安全を誓 う)」ことを稽古の心構えとしています。
【修得内容】
初心者から組太刀(くみたち)の考えを取り入れながら、坐業(すわりわざ)、立業(たちわざ)の居合形を修得します。
また居合形以外に、構え、祓太刀(はらいのたち)を修得します。
居合道に求めるもの
稽古を積み重ねることで、剣技だけではなく礼儀を身に付け、将来の目標を持つことで日々の生活を充実させることができます。
居合道が老若男女・国籍を問わず多くの人から愛される理由は、各々が「現代に求められる武士道とは何か?」と追及しながら、己に向き合うことができる からです。
また、稽古に励む同志ができることで、切磋琢磨しながらお互いを理解し合い、コミュニケーションを大切にすることで強い絆が生まれます。
こうした居合道によって、現代になくてはならない士道を極めたいと考えています。